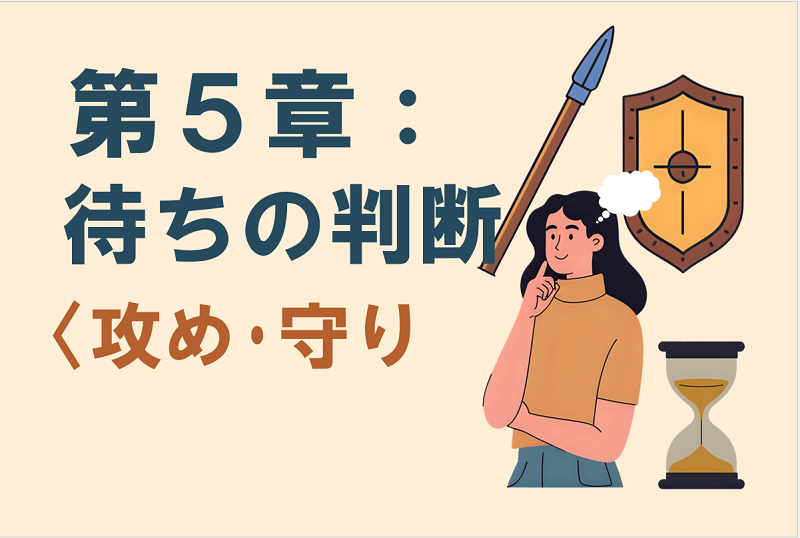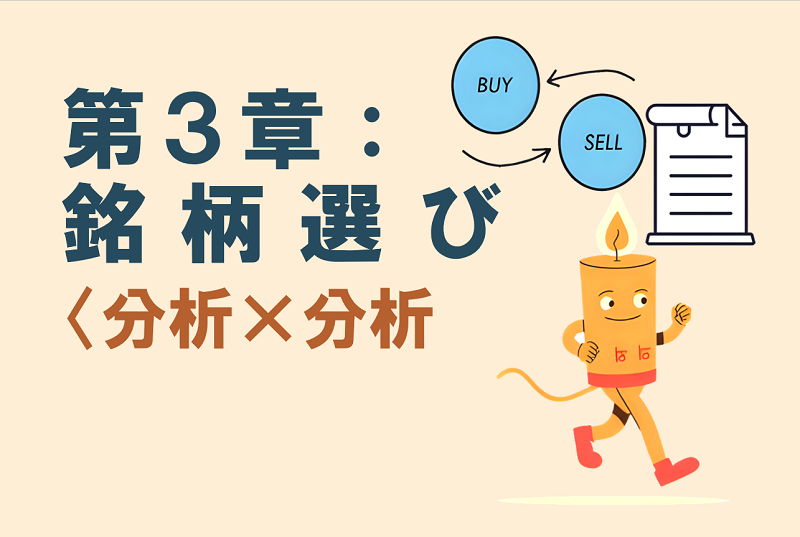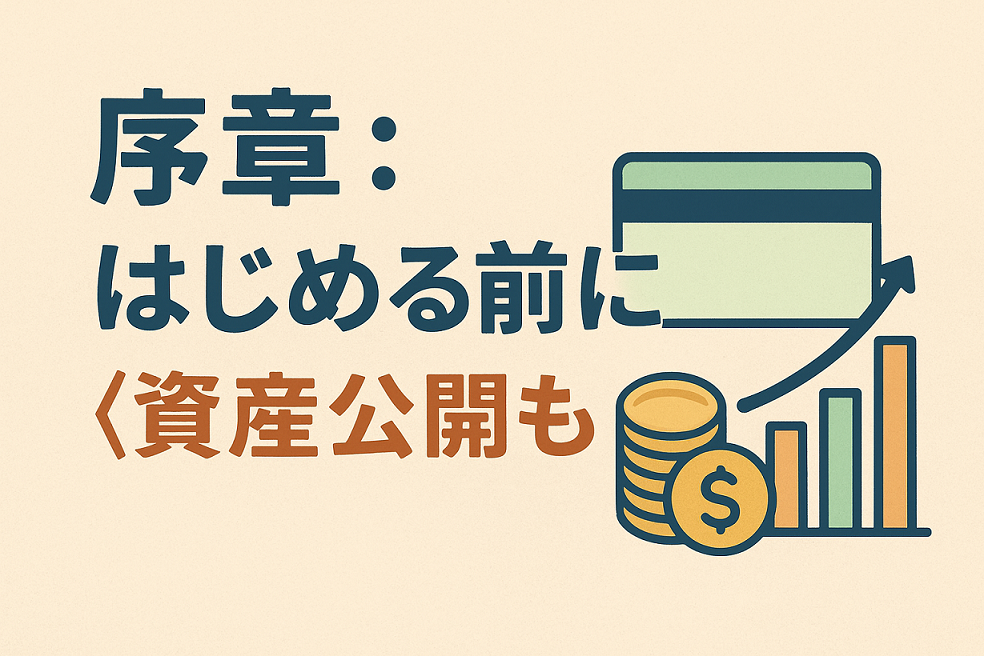こんにちは、アカナレッジです。
前回の投稿は、「第1章:口座開設〈証券アプリの設定〉」という題目の準備編でした。
口座開設の注意事項を示したほか、証券アプリをテクニカル分析に適した表示へ設定変更しました。
また、ホーム画面でよく目にする、日経225のチャートについて実際に画像を示し、
ボリンジャーバンド・RSI・MACD等のテクニカル指標に基づいて確認することを説きました。
しかし、前回は設定の記事でしたので、中身についてはこれからです。
今回は、具体的な日経平均株価チャートの使いどころについて解説します。
個別の銘柄に入る前に、マクロな視点で「市場全体の流れ」を押さえる方が無難です。
当ブログで紹介する「堅実スイング投資」では国内株式を対象としています。
そのほか注意事項は、序章:はじめる前に の記事を参照ください。
2-1. なぜ全体トレンドを見るのか〈大前提〉
株式取引の大前提は、安値で買って高値で売ることです。
個別銘柄のチャートだけを見て売買を判断してしまうと、市場全体が下落トレンドのときには「安くてもさらに下がる」というリスクがあります。
そのため、「堅実スイング投資」のように対象が日本株の場合には、常に日経平均で全体トレンドを把握することが重要です。
全体の流れに沿った取引を心がけることで、損失リスクを抑えられ、利益を最大化できます。
🔷日経平均株価
日本の代表的な株価指数で、東証一部上場の225銘柄の株価をもとに算出されます。
個別株だけでなく市場全体の方向性を見る指標として非常に便利です。
ちなみに、TOPIX(東証株価指数)と日経平均は、銘柄数や計算方法が異なるため、使い分けが必要です。堅実スイング投資では、主に日経平均を参考にしています。
2-2. 過去の相場の波を知る〈年足で見る〉
市場は常に上昇と下落を繰り返しています。
下図は、過去の長期的な日経平均株価チャートです。

グラフ上でもわかるように、過去には以下のような大きな波がありました。
🔷ITバブル(1990年代後半〜2000年)
インターネットやIT関連企業の成長期待で株価が急騰
主因は 技術革新・投資熱・過剰な期待
政治要因は限定的(景気政策や規制緩和は多少影響)
🔷リーマンショック(2008年)
金融システムの不安と連鎖的売りによる株価の急落
主因は 金融機関のサブプライムローン問題と世界的信用収縮
政治的要因(規制や金融政策)は間接的に関与
🔷コロナショック(2020年)
政治対応(ロックダウン、補助金政策、日米の金融政策など)が市場に影響
主因は 感染症拡大による経済活動の停止
株価は一時的に暴落したが、政府・中央銀行の政策で回復
こうした過去の波を知ることで、相場の「上昇と調整のサイクル」を理解でき、銘柄選びや売買タイミングの判断に役立ちます。
株価の暴落が起きた時に、「巻き込まれて損失を生むか」、あるいは「損失を最小限に抑えて安値買いのチャンスと捉えることができるか」、は日々の分析次第です。
市場は常に上昇と下落を繰り返すことから、あなたが株を保有すれば、その資産の推移もまた上下に変動することを心得ておきましょう。
2-3. トレンドを分析する〈日足・週足・月足で見る〉
日経平均は平均価格であり個別の銘柄とは異なりますが、チャートの表示やその見方は共通しています。
株価チャートを見るとき、つい「日足」だけに注目しがちです。しかし、短期の動きだけを見ていると、長期的なポジションを勘違いしまうことがあります。実際のトレンド分析では「日足・週足・月足」を組み合わせて判断することが重要です。
下図は、2025年9月19日現在の日経255のチャート「日足・週足・月足」です。

日足については次のように推察できます。
🔷上昇局面の特徴
ボリンジャーバンド:黒線(+3σあたり)に沿って高値が止まる。バンド付近では一時的な過熱感を示す。
RSI:極大値を取り、ピークで 80を超える。買われすぎゾーンに入ることで天井感が出やすい。
MACD:極値を取り、ピークの規模はそのときの上げ幅に相当。大きな山は強い上昇トレンドを示す。
🔷下降局面の特徴
移動平均線:緑のライン(MA2中期線)が下値の目安になっている。短期線と中期線が交差する場面は「トレンド転換点」として注目される。
RSI:下降トレンドでは、RSIが極小値を取り、20前後まで下がる。この水準は「売られすぎ」を示し、一時的な反発(リバウンド)が起こりやすい場面。
MACD:MACDは極値を取る。特に 、MACDライン(青)が大きく下に振れるほど、下落の勢い(スケール)が強い と判断できる。
週足と月足も、基本的には同じ視点です。画像のみ示します。


それでは続けて、9月19日現在時点のトレンドは上昇・下降のどちらでしょうか?
すなわち、買い時でしょうか?売り時でしょうか?
日足でみると、
ボリンジャーバンド付近、RSI80超え、MACDシグナルもピークをつけている。
⇒短期的には、トレンドが上がり切った後の下降トレンド気味です。
週足でみると、
ボリンジャーバンド付近ではないが、RSIが数週間にわたり80寄り付き。MACDも同様。
⇒中期的にも、十分に上がり切っている状態といえる。いつ下がってもおかしくない状況。
月足でみると、
ボリンジャーバンド付近でなく、RSIは上昇気味。MACDライン赤が1本目。
⇒長期的には、上がり途中で、上昇トレンドは崩れていない。ただし、2025年度以降ずっと陽線を続けており、RSI が連続で高めで過熱感が蓄積しているので、下降のシグナルはないものの反転の危機感あり。
「堅実スイング投資」に基づく判断では、今は「売り時に近づきつつあるピーク」と見ています。
もしポジションを持っているなら、利確を考えるか、すでに上がってきている銘柄については警戒して売り準備を進めておくのが堅実です。
逆に、新規で買いを入れるなら、押し目が確認できる場面を待つほうがリスクが抑えられると思います。
2-4. 全体トレンドと銘柄選びの関係〈例外あり〉
ここまで、日経平均株価を題材にしながら、上昇トレンド or 下降トレンドを分析してきました。
判断の際には、ボリンジャーバンド・RSI・MACDといったテクニカル指標を用いることで、
「なんとなく上がりそう/下がりそう」といった感覚的なものではなく、数値に基づいた考察が可能になります。
テクニカル分析の強みは、過去のデータから傾向を見抜き、再現性のある判断につなげられる点にあります。もちろん「必ず当たる予測」ではありませんが、感覚や噂に流されず、冷静に市場をとらえる助けになるでしょう。
株式取引の大前提は、安値で買って高値で売ることでした。簡潔には、底値付近で買い ⇒ 過熱感のある高値付近で売りに出して、利確すればよいのです。
ただし、完璧に底と天井を当てるのは不可能なので、
・分割して買う / 売る。
・損切りルールを徹底する
といったリスク管理も同時に重要になります。
このようなリスク管理は、個別銘柄ごとの対応になるので、次回以降で解説します。
ーおわりに
ここまでご覧いただきありがとうございます。
全体トレンドを把握することはできたでしょうか。
直感で判断する必要はありません。一時の決断は、むしろ思い込みを生じてしまいます。
日々繰り返しチャートを観察することで、自分の分析の精度を上げることが重要です。
それが1つの堅実さだと思います。
次回は、第3章:銘柄選び〈スクリーニング〉の連載予定です。
X(旧Twitter)などと連携して情報を発信いたします。皆様からのコメントも歓迎いたします。